 旧館より
旧館より 人によって違う「ゆっくり」
お客様や同僚から言われる「この仕様をドキュメントにまとめてもらえますか?急いでいないので、"ゆっくり"で良いですよ」という言葉。よくある会話ですが、この「ゆっくり」の捉え方によっては、ちょっと痛い目を見るかも知れません。「ゆっくり」の違い「...
 旧館より
旧館より  改善
改善 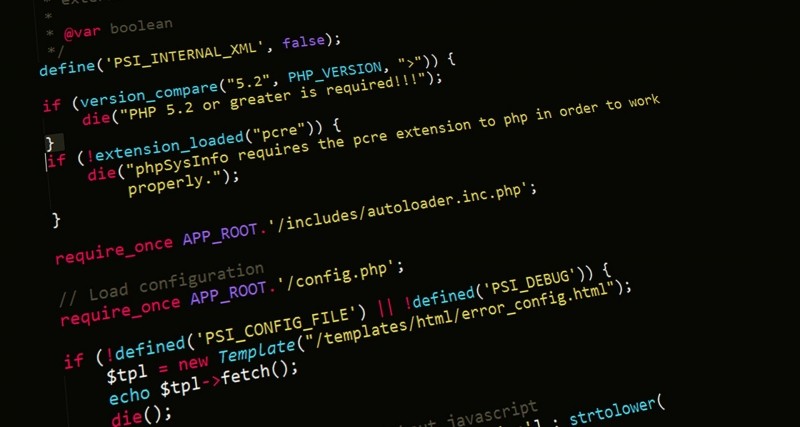 ソフトウェア開発
ソフトウェア開発