 仕事のやり方
仕事のやり方 ホワイトボードを使わない会議はあり得ない
色々な意味でカルチャーショックなプロジェクトの話です。お客様との打合せ…議題は複雑で、図解をしたりして、何らかの「見える化」などの対策をしないとアッと言う間に「空中戦」になること必至のものでした。#少なくとも私にはそう思えました。で、私達の...
 仕事のやり方
仕事のやり方  チームビルディング
チームビルディング  旧館より
旧館より 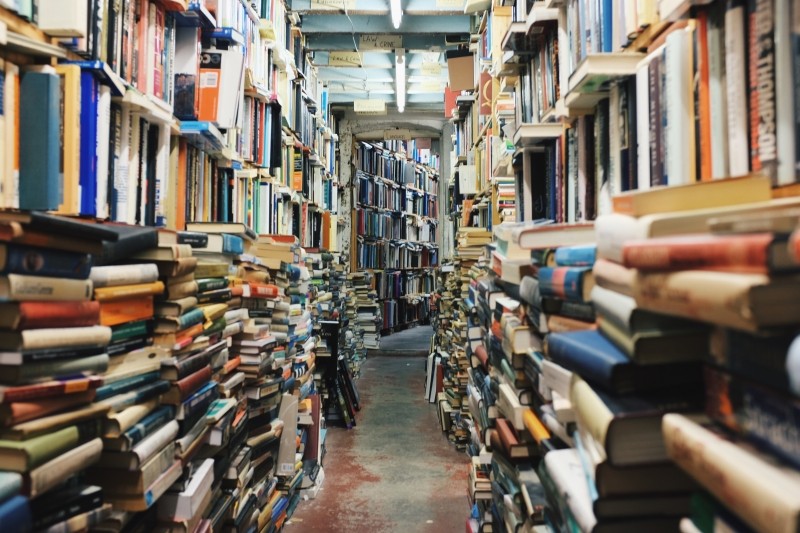 旧館より
旧館より