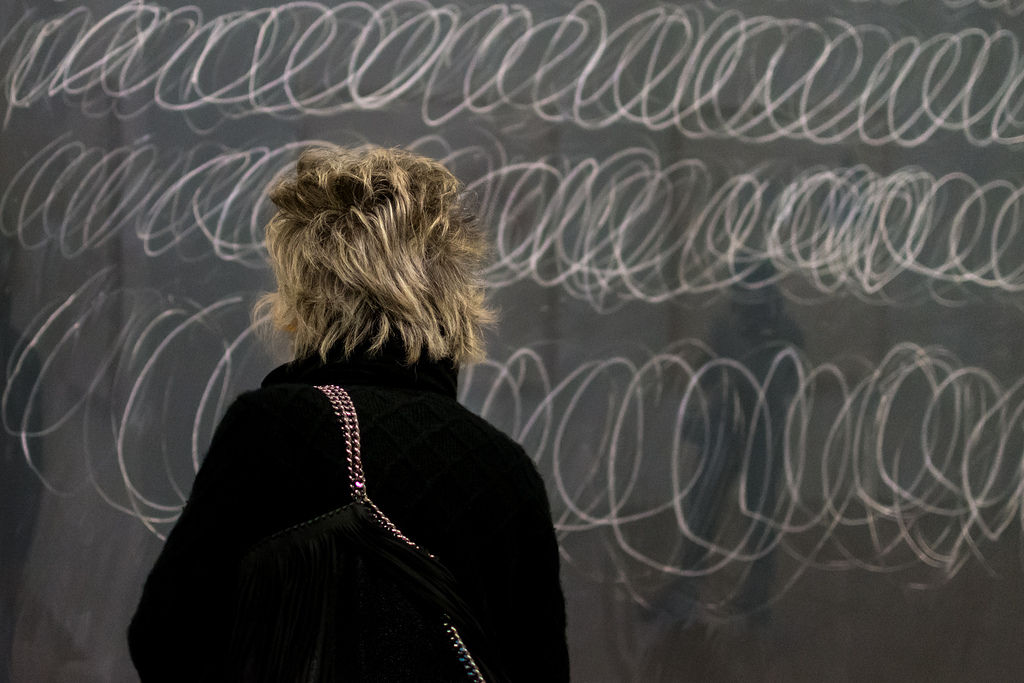 チームビルディング
チームビルディング 週次フリカエリ
最近、お客様への納品が終わったプロジェクトで採用した「プチフリカエリ」について書きます。(私の所属企業、かつ、知っている範囲では)「フリカエリ」は(大規模プロジェクトでは)工程の終了時、(小規模プロジェクトだと)プロジェクト終了時に行うこと...
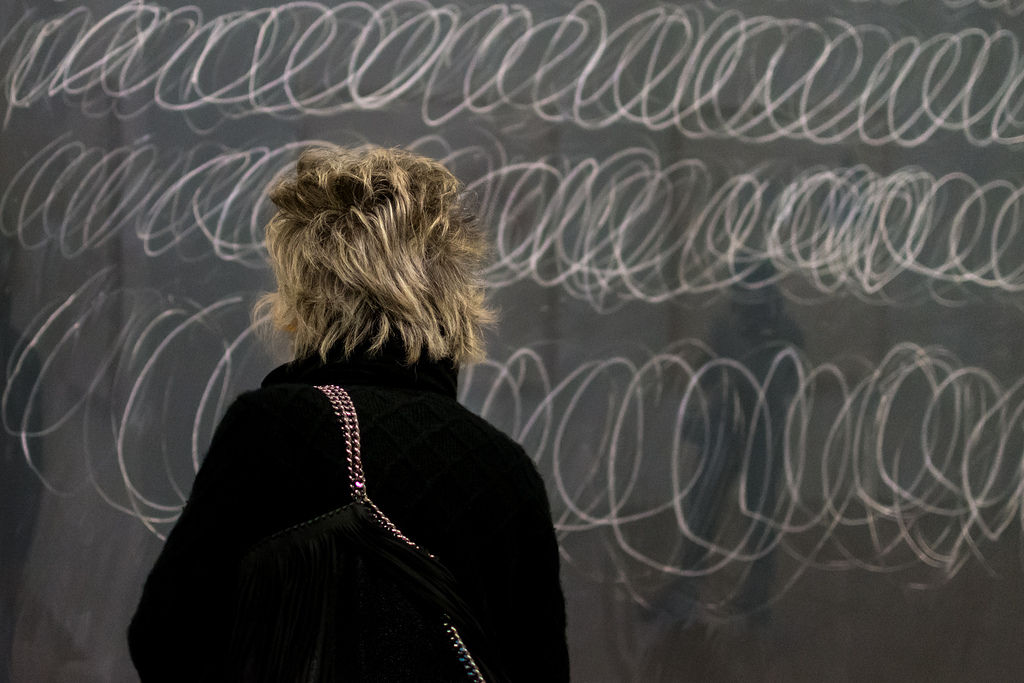 チームビルディング
チームビルディング 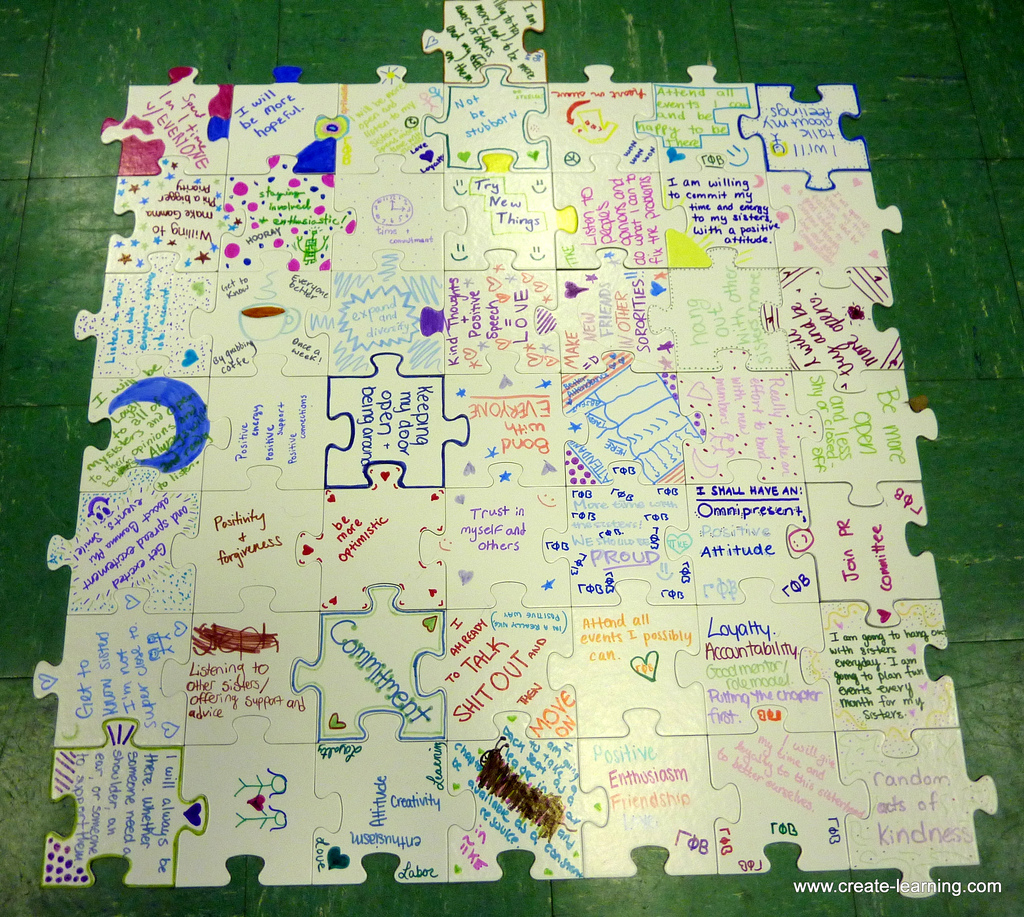 改善
改善  改善
改善  旧館より
旧館より