 仕事のやり方
仕事のやり方 (研修主催者が)良いフィードバックを得るためには
社内のある研修に参加した時(とその後)に「良いフィードバックを得るためには…」を考えさせられたので書いてみます。その研修は、(何度も行われているものですが)私が参加した回はそれまでのやり方を大きく変えたとのことでした。#私は「それまで」をあ...
 仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方 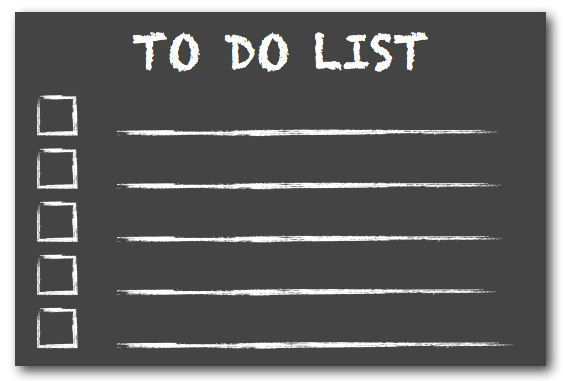 仕事のやり方
仕事のやり方  日常
日常