 Agile
Agile Regional Scrum Gathering Tokyo2024 に参加してきました #RSGT2024
自分にとって「この場には必ず参加したい。できればスピーカーとして」という場があります。その1つがこのRegional Scrum Gathering Tokyo(RSGT)です。というわけで、 そのRSGT2024に参加してきましたまず、実...
 Agile
Agile  Scrum
Scrum  勉強会
勉強会 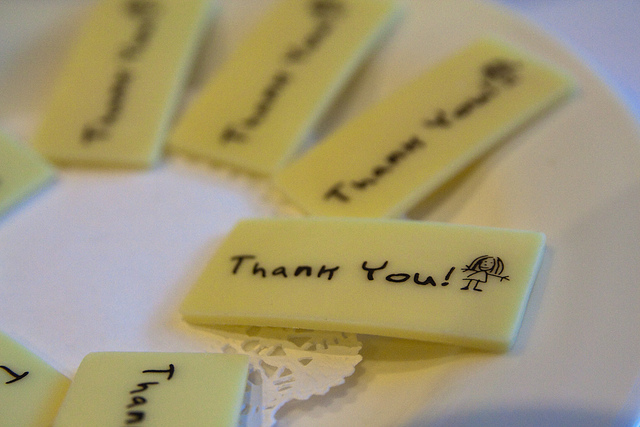 チームビルディング
チームビルディング  旧館より
旧館より