 Agile
Agile Regional Scrum Gathering Tokyo2021 に参加してきました #RSGT2021
もう4週間前になりますが、Regional Scrum Gathering Tokyo2021(#RSGT2021)に参加してきました今回はハイブリッド開催でしたが、これまでとは違う楽しみ方を見つけることができましたこの状況で、開催してくれ...
 Agile
Agile  Agile
Agile 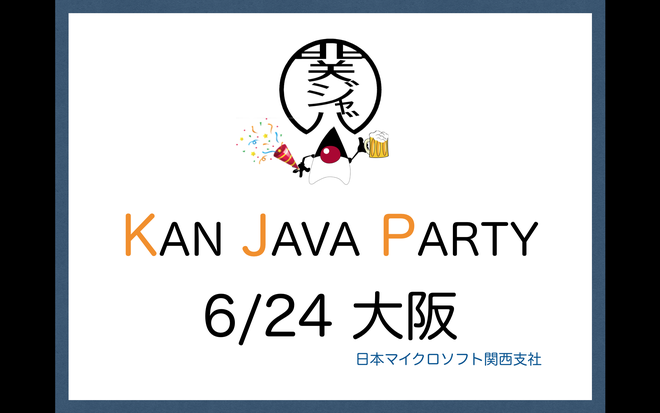 DevLOVE関西
DevLOVE関西