 DevLOVE関西
DevLOVE関西 2017年のふりかえり
2017年のふりかえりです。2017年は総じてどんな年だったか?5段階なら4という感じです。ギルドワークスとして「正しいものを正しくつくる」という旗を掲げて活動しているギルドワークスとして、そこにより向かうためにいきなり最強チームや仮説検証...
 DevLOVE関西
DevLOVE関西  Agile
Agile 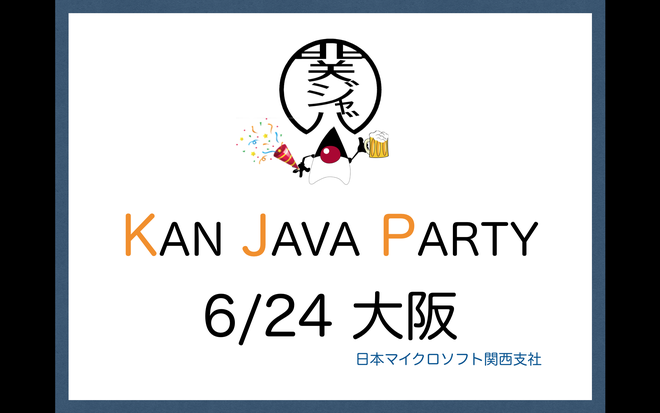 DevLOVE関西
DevLOVE関西  Agile
Agile  Scrum
Scrum  ギルドワークス
ギルドワークス