 DevLOVE関西
DevLOVE関西 2019年のふりかえり
2019年のギルドワークス2019年のニュースやお知らせは全部で37本でした。2018年は38本だったので前年と同じくらいです。主な出来事デブサミでのエンジニア相談ブース5周年パーティを開催市谷さんが「正しいものを正しくつくる プロダクトを...
 DevLOVE関西
DevLOVE関西  Agile
Agile  Agile
Agile  DevLOVE
DevLOVE 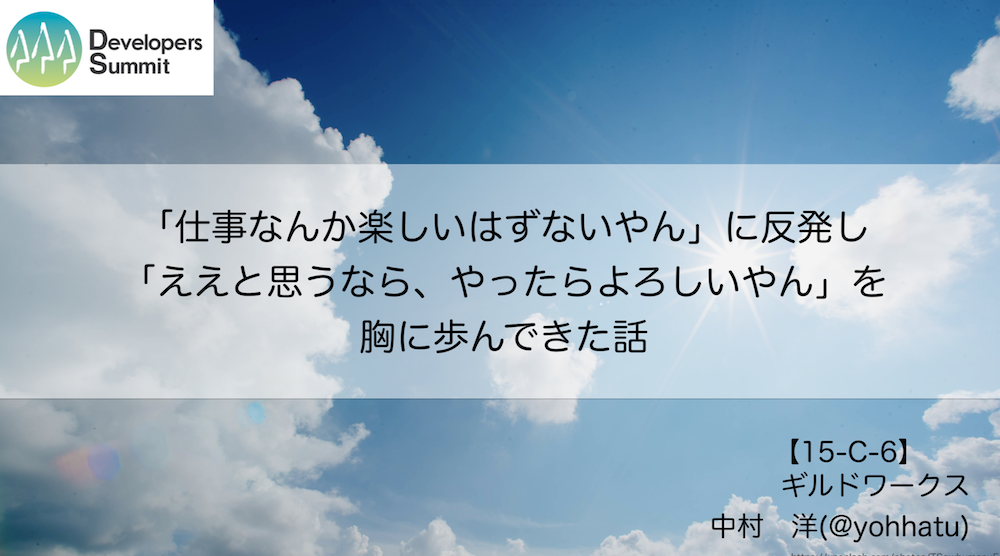 コミュニティ
コミュニティ  コミュニティ
コミュニティ 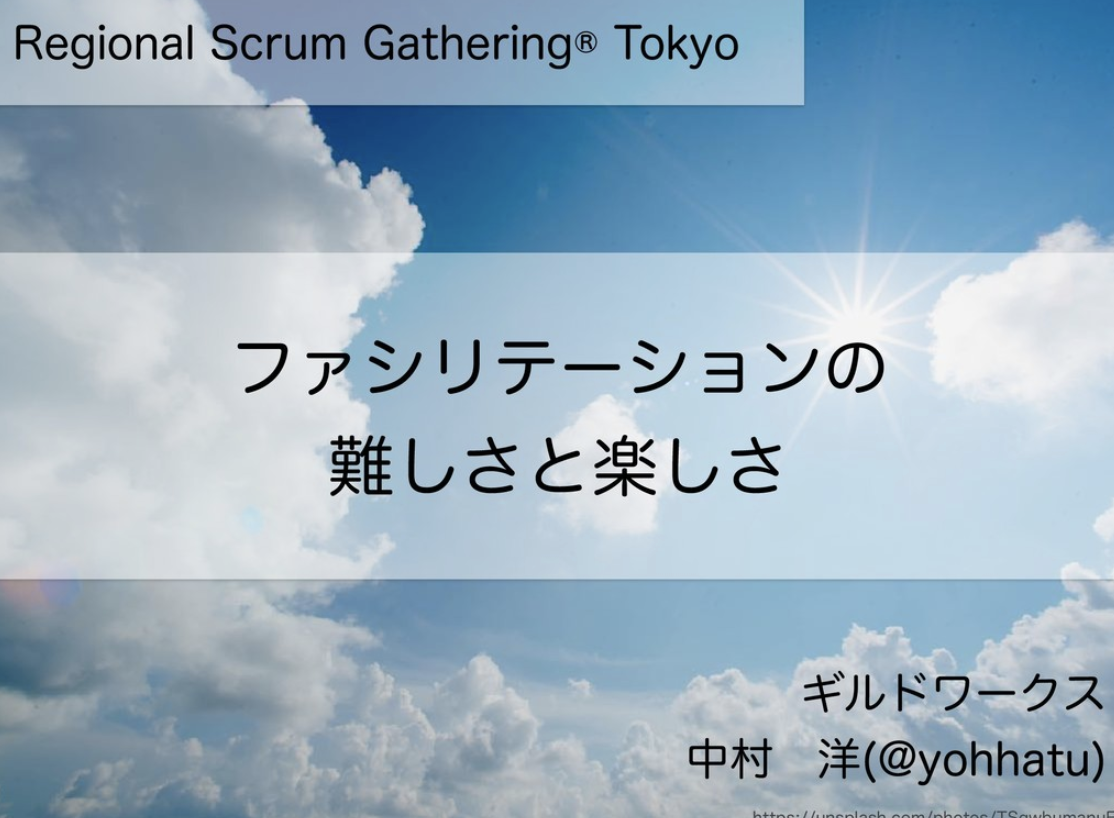 Agile
Agile  Agile
Agile