 Agile
Agile Regional Scrum Gathering Tokyo2025 に参加してきました #RSGT2025
Regional Scrum Gathering Tokyo(RSGT)2025に参加してきました。まず、実行委員、ボランティアスタッフのみなさん、(毎回のことですが)こんなステキな場、ありがとうございました!「スクラム"だけ"を正しくや...
 Agile
Agile  DevLOVE関西
DevLOVE関西  Agile
Agile  Agile
Agile  Agile
Agile  Agile
Agile  コミュニティ
コミュニティ  Agile
Agile  Agile
Agile  DevLOVE
DevLOVE 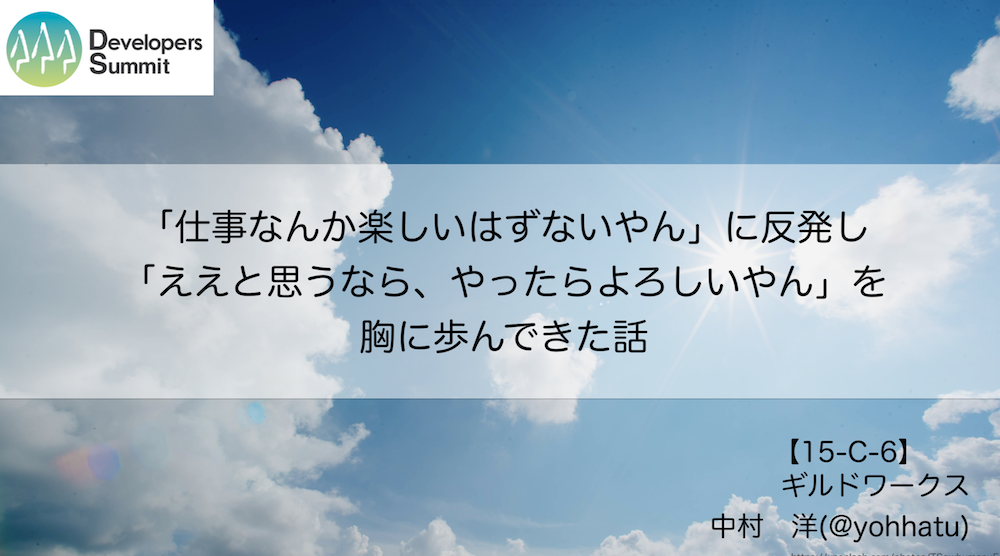 コミュニティ
コミュニティ  コミュニティ
コミュニティ 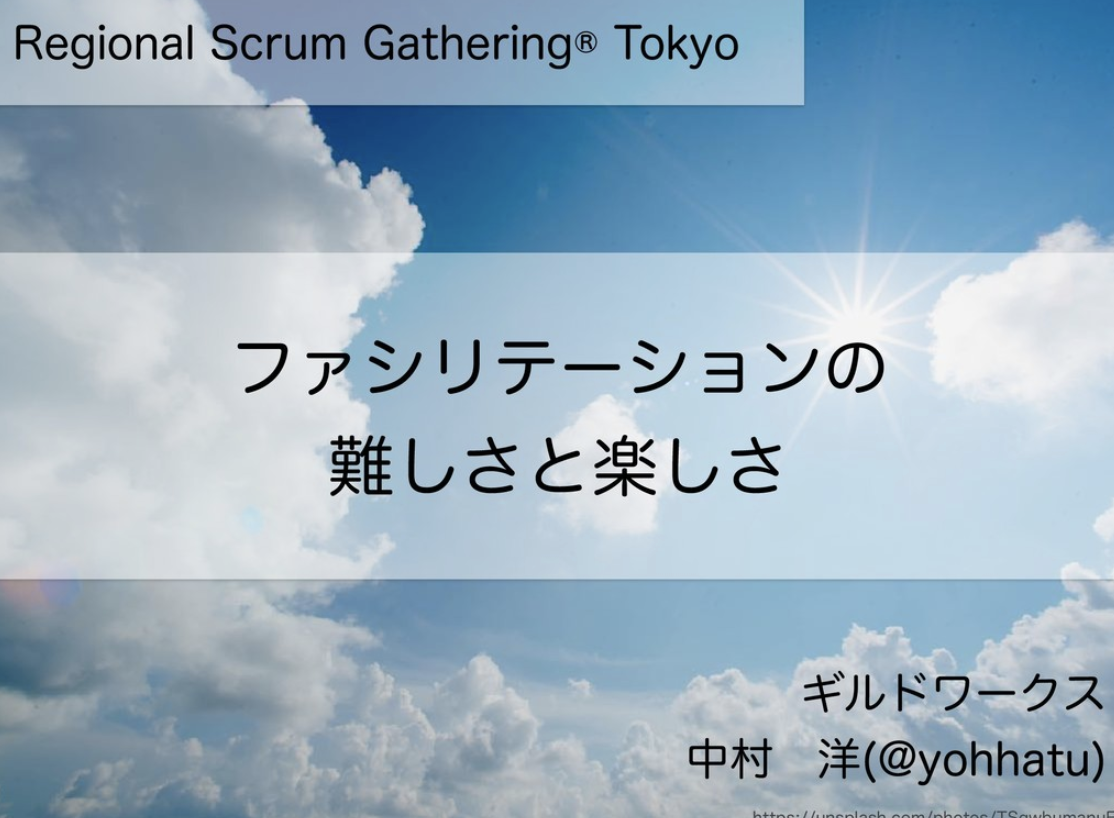 Agile
Agile  Agile
Agile  Agile
Agile 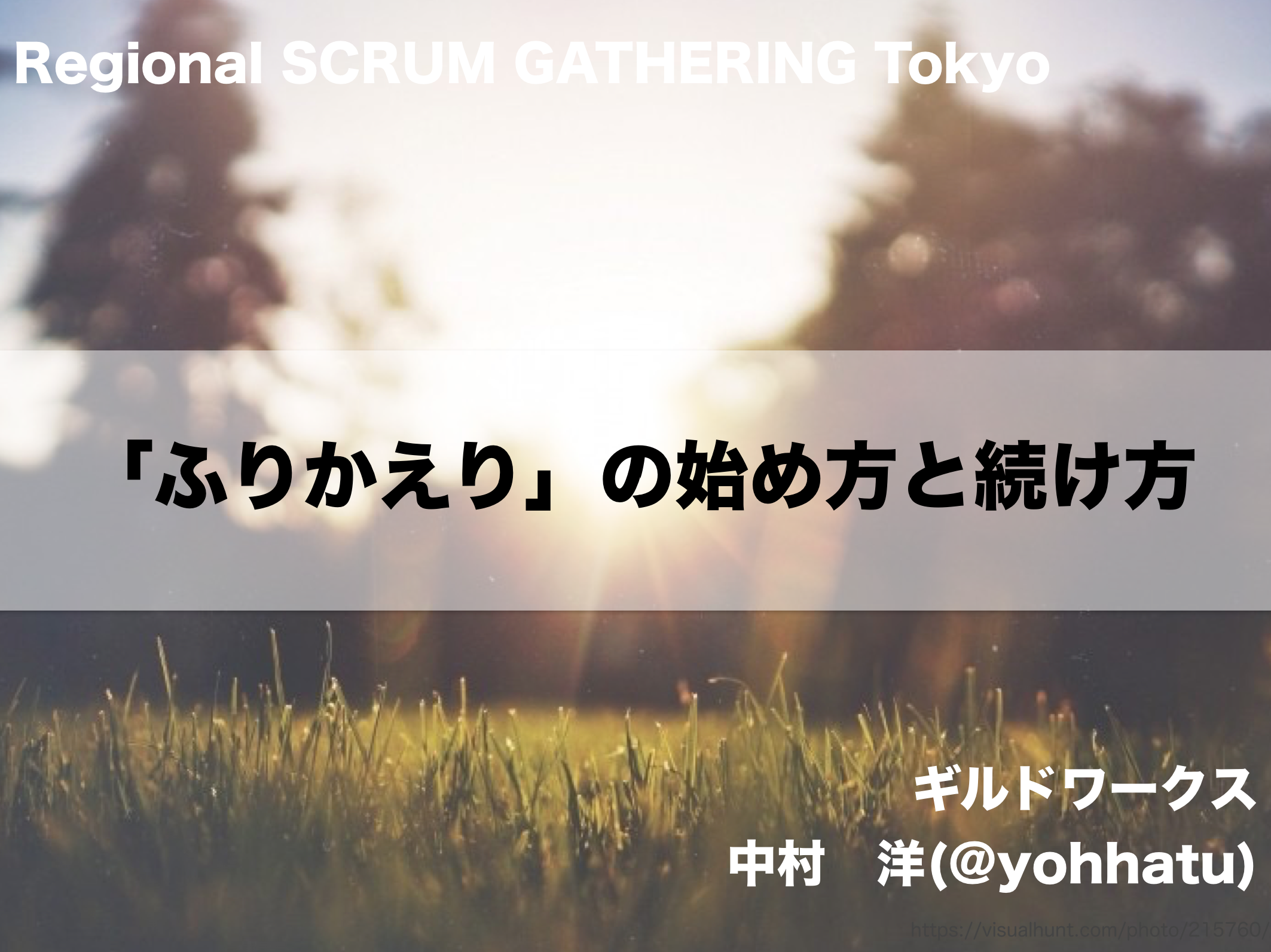 Agile
Agile  Agile
Agile  ギルドワークス
ギルドワークス  DevLOVE関西
DevLOVE関西  DevLOVE関西
DevLOVE関西