 Agile
Agile Regional Scrum Gathering Tokyo2025 に参加してきました #RSGT2025
Regional Scrum Gathering Tokyo(RSGT)2025に参加してきました。まず、実行委員、ボランティアスタッフのみなさん、(毎回のことですが)こんなステキな場、ありがとうございました!「スクラム"だけ"を正しくや...
 Agile
Agile  レッドジャーニー
レッドジャーニー  仕事のやり方
仕事のやり方  Agile
Agile  仕事のやり方
仕事のやり方 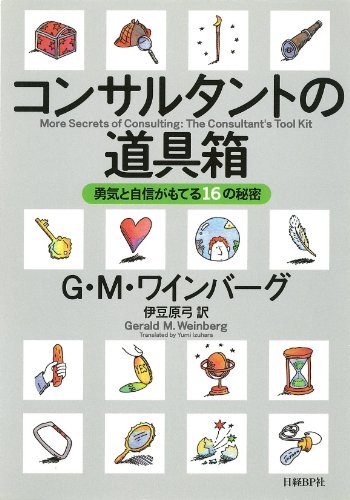 仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方 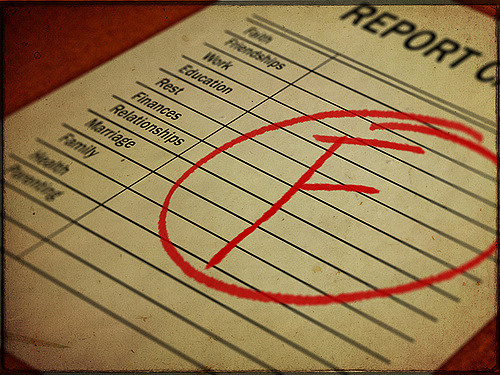 仕事のやり方
仕事のやり方 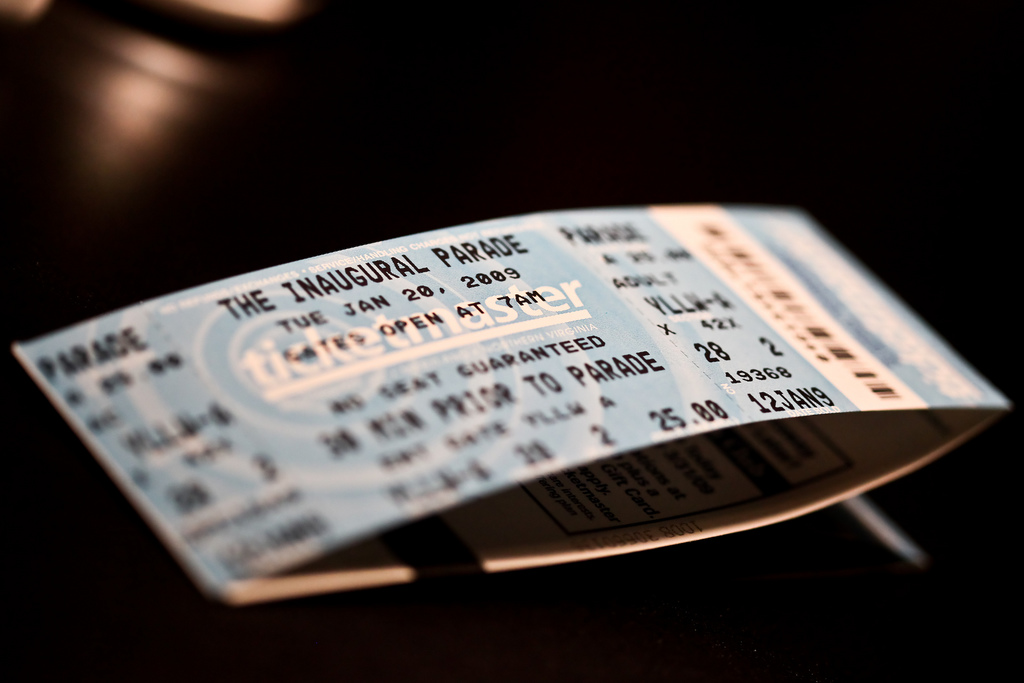 Redmine
Redmine  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方 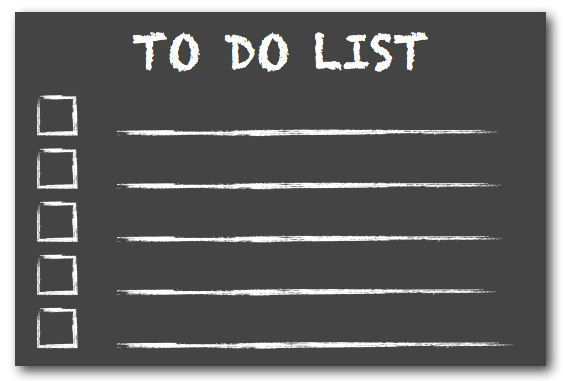 仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方  仕事のやり方
仕事のやり方